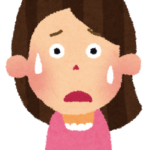
猫って水をあまり飲まないって聞くけど、飲まなさすぎじゃない?
猫たちは本能的にあまり水を飲まない動物です。でも、そのままドライフード中心の食生活を続けると、知らず知らずのうちに水分不足になりやすくなります。
水分不足の状態が続くことで、尿路結石や腎臓トラブルといった深刻な健康リスクが高まる可能性もあります。


この記事では猫の行動パターンや現代の飼育環境の変化もふまえ、猫たちの「水を飲まない理由」と「飲ませるための現実的な工夫」を丁寧に解説していきます。
猫たちは「水を飲まないこと」が普通な反面、そのままにすると健康リスクが高まる可能性があります。習性を理解しつつ、飼い主さんが少しだけ意識を変えることで、猫たちの暮らしはより安心なものになります。


〈プロフィール〉
- 猫の飼育歴:6年目
- 迷い猫「くぅ」、保護猫「みり」と生活中
- 猫との遊びを充実させるアイテムを模索中
- キャトログを使い続けて【16ヶ月目】
猫が水をあまり飲まない…、それって普通?
帰宅したときに、水がまったく減っていないとちょっと心配になりますよね。



どこか体調が悪いのかな?
実は猫はもともと水をあまり飲まない動物です。だからといって、「そのままにしておいて良いかどうか」は少し別の話です。この章では、猫の本来の習性と現代の暮らしの中で注意すべきポイントを紹介します。
猫はもともと水をあまり飲まない動物
猫の祖先は、アフリカや中東の乾燥地帯に生息していた「リビアヤマネコ」。 砂漠のような環境で水を見つけるのは簡単ではなかったため、猫の体は“少ない水でも生きられるように”進化してきました。
そのため、猫には次のような特徴があります:
- 尿を濃縮して、少ない水分で排泄できる
- 飲むよりも、獲物の体液から水分をとる傾向がある
つまり、「水をあまり飲まない」のは猫の“本能”に由来しています。問題は、この“本能”がそのまま現代の暮らしに当てはまるとは限らない、ということです。もちろん猫それぞれの個体差もあるので、日々の観察も重要になってきます。



「くぅ」は水をよく飲むけど、「みり」はあまり飲まないので猫によって様々でした。
「飲まないのが普通だから大丈夫」と思って放置すると、実は水分不足がじわじわ進んでしまう。それが、病気や不調のリスクを高める原因にもなります。
だからこそ、猫の習性を知ったうえで「どう飲ませていくか」を考えることが、飼い主さんの大切な役割なのです。
ドライフード主体の生活では猫の“習性”がリスクになる


室内飼育が推奨されている現在では、多くの猫たちが狩りではなくキャットフードを食べています。
特に日本のドライフードは水分量が10%前後しかありません。野生の猫が食べていたネズミなどは、約70〜80%が水分なので、食事だけで水をとることが難しい環境になっているのです。
ドライフードは通常、水分含有率が 20% 未満です。ただし、欧州(14% 未満)、日本(10%程度以下)、およびブラジル(12% 未満)を除きます。
引用:ペットフードの形状の違い | CentreSquare | Purina Institute
また飲水量が不足すると、以下のようなリスクが高まります:
脱水症状とかかわっている病気・疾患としては次のものがあります。
引用:猫の水分補給方法とは?水分の重要性と与え方を解説 | ペットと暮らしのWebマガジン|日本ペットフード
- 腎臓病(急性腎不全・尿毒症など)
- 猫下部(膀胱・尿路)の病気(尿路結石症・膀胱炎など)
- 熱中症
水をあまり飲まない体質だからこそ、飼い主さんが意識して水分を補う工夫が必要になります。
1日に必要な水分量の目安をチェック





どのくらいの水を飲んでいれば良いの?
猫は砂漠に住む動物で一般にはあまり水を飲まないとされており、理想的な1日の飲水量は体重1kgあたり30〜50ml程度です。
引用:猫が水を飲まない|猫のよくあるご相談|猫と暮らすお役立ち情報|ニャンとも清潔トイレ|エステー株式会社
体重ごとに計算すると、以下のような数値が飲水量のおおよその目安になります。
| 猫の体重 | 一日の飲水量の目安 |
|---|---|
| 3kg | 90~150ml |
| 4kg | 120〜200ml |
| 5kg | 150〜250ml |
| 6kg | 180〜300ml |
※これらの数値はあくまで目安です。猫たちの状態や環境によっても必要な水分量は異なってきます。
猫たちが普段どのくらいの水を飲んでいるか?チェックするための方法はいくつかあります。
- メモリ付きの水皿を利用する
- 入れた水と戻した水の量を計測する
- おしっこ回数や尿量を直接観察する
- Catlog Board2を利用する
- 脱水サインをチェックする
まずはメモリのついた水皿で水分摂取量を確認することから始めてみましょう。
>>【猫が水を飲んでるか、わからない…】自宅で出来る5つのチェック方法
猫が水を飲まない7つの理由と“すぐできる”対策





やっぱり、飲んでなさそう…
猫が水を飲まない理由は、性格や体質だけでなく、環境や体調の影響も大きく関係しています。ここでは、初心者の飼い主さんでも気づきやすく、今日から試せる7つの原因と対策を具体的に解説します。
水の温度やにおいが気に入らない
猫はにおいや温度にとても敏感です。水が古くなっていたり、温度が適していないと、それだけで口をつけなくなることがあります。
とくに水道水に含まれる塩素(カルキ)のにおいは、人間にはほとんど気にならなくても、猫にとっては不快な場合があります。カルキのにおいが気になって、水を避ける猫もいるようです。
参考:【獣医師監修】猫が水を飲まないときの対処法 ~原因から解決策まで詳しく解説~|アイシア株式会社 |
- 1日に2回以上、水を入れ替える
- 常温の水を用意する(冬はぬるま湯にしてみる)
- 水道水が気になるようであれば、沸騰→冷却や浄水器の使用も検討する



水道水はダメなの?
飲ませるのは水道水で充分。飲める水ならOKです。
引用:猫の腎臓病がわかる本 宮川優一著 女子栄養大学出版部 P.41
猫の好みは千差万別です。水の温度を工夫したり、カルキ臭さが気になる場合には一度煮沸→冷却してからあげてみましょう。



冬場はぬるま湯にしてみるのがおすすめです。
器の形・素材・置き場所が合わない
猫によっては、ヒゲが器のフチに当たるのを嫌がる子や、金属製の器の反射が苦手な子もいます。器の素材や形状を見直すだけで、飲水量が改善されることがあります。
- 平たくて広めの器に替えてみる
- 陶器やガラス製など、においや音が少ない素材を選ぶ
- 水皿の高さを変えてみる
さらに大切なのは、猫が「わざわざ飲みに行く」のではなく、「通りがかりについでに飲める」環境を作ることです。



高さを工夫するだけでも飲むようになったので、おすすめです。
- 猫の生活動線(通り道や休憩場所の近く)に水皿を置く
- リビング、廊下、キャットタワーの近くなどに複数設置する
- どの場所が落ち着くか、猫自身に選ばせる
猫が自由に、ストレスなく水を飲める環境が整えば、自然と飲水量も安定しやすくなります。多頭飼いの場合も、それぞれの猫が安心して使える場所を意識して配置してみましょう。
流れる水しか飲まないタイプの猫



キッチンの蛇口から水が流れると寄ってくるんだよな…。
そんな様子を見たことがある飼い主さんも多いのではないでしょうか。実際に、猫の中には静止した水よりも“流れる水”を好んで飲むタイプがいます。



「くぅ」は流れる水が一番好きです
すべての猫が流れる水を好むわけではありませんが、飲水量が増えるきっかけになる場合も多いため、一度試してみる価値はあります。



自動給水器が気になってきたけど、どうなんだろう?
【猫の自動給水器はやめた方が良い?】迷った際の選び方とメリット・デメリットという記事で自動給水器の導入について詳しく解説しているので参考にしてみてください。


ウェットフードから水分をとっている
猫が水皿から飲んでいないように見えても、ウェットフードからしっかり水分をとっていれば、必要以上に心配しすぎる必要はありません。
1日すべてをウェットフードで与えている場合
この場合は、1日の水分量はほぼ足りていると考えられます。ウェットフードには約70〜80%の水分が含まれており、水皿の水をそれほど飲まなくても、水分補給はできています。
水の飲み方が気になっても、尿や便の状態に異常がなければ、今のスタイルを安心して続けてください。
ドライとウェットを組み合わせている場合
この場合は、食事からの水分摂取量は一部補えてはいますが、飲み水からの摂取も重要です。特に朝ドライ、夜だけウェットといったスタイルでは、1日の総水分量が不足気味になることがあります。
- 水皿の設置場所や素材を工夫して飲みやすくする
- ウェットの回数や量を少しずつ増やす
- スープタイプやちゅ〜る水で補助的に補給する
「そこまでしなくても…」と思われるかもしれませんが、慢性的な水分不足は尿路結石や腎臓の負担につながる可能性があるため、早めの対策が安心です。



「みり」に結石があることが判明してからはウェットを併用しています。
ときどきしかウェットをあげていない場合
この場合、水分不足のリスクが比較的高いといえます。飲水量が少ないまま放置すると、健康トラブルにつながる可能性もあるため、食事と飲み水の両面からの水分補給を意識しましょう。
環境の変化やストレスの影響を受けている
猫は周囲の変化にとても敏感です。引っ越しや模様替え、来客、生活音の変化、トイレや食事スペースの変更など、些細なことがストレスになることがあります。
猫のストレスサインのひとつに「飲水量の減少」があるといわれています。飲みたそうにしているのに水皿に口をつけない、そんな様子が見られる場合は、ストレスで落ち着いて飲めない状態かもしれません。
- 急な模様替えや配置換えは避ける
- 生活音の大きな場所(TV前・玄関近く)は避ける
- 水皿をトイレや人の動線から離れた、静かな場所に置く
- お気に入りの寝場所近くなど、猫がリラックスしやすい位置に設置
また、多頭飼いの場合は他の猫との関係にも配慮が必要です。飲むたびに周囲を警戒しているような仕草があれば、水を飲みにくいと感じている可能性があります。


口内の痛みや体調不良の可能性がある
猫が急に水を飲まなくなる背景には、口の中の違和感や、体の不調が関係している場合があります。とくに、高齢の猫やもともと食が細い猫の場合は、ちょっとした痛みでも飲食を避ける傾向があるようです。
例えば以下のような変化が見られた場合は、体調の変化が関係している可能性があります。
- 水を飲もうとした後、口元を気にしている様子
- 食事の様子にも変化がある
- 口臭がきつくなる
普段と違う様子が続く場合は、念のため動物病院に相談することをおすすめします。猫は不調を隠す傾向があるため、飼い主さんが日々の変化に気づくことが早期発見につながる大切なステップです。
参考:水を飲まない / 猫の病気|JBVP-日本臨床獣医学フォーラム
参考:【口内炎】猫の口内炎とは?症状や治療法を解説 | 若山動物病院
実は飲んでいるのに(飼い主さんが)気づいていない
「水を飲んでいる姿を見かけない」「水皿が減っていない」——そんな不安を感じる飼い主さんは多いです。
でも実際には、飼い主さんが見ていない時間帯にこっそり飲んでいることはよくあります。特に夜間や、人のいない時間に水を飲むのが習慣になっている猫も少なくありません。
また、水皿の水の減り方は少しずつなので、目視では変化に気づきにくいこともあります。そんなときに頼りになるのが「見える化」できるツールです。



水を飲む量が減っているか、どうやって確認するの?
猫の飲水量を確認する最も簡単な方法は、メモリのついた水皿を利用することです。毎日の猫の行動(飲水回数、おしっこの量など)を自動で記録する場合は、Catlog Board2を利用してみるのもオススメです。
他にも、猫が水分摂取をしているか確認する方法はあります。詳しくは、【猫が水を飲んでいるかわからない…】自宅で出来る5つのチェック方法という記事を参考にしてみてください。



Catlog Board2を使うようになって、猫のトイレに対する意識も変わりました。


まとめ|水を飲まない“習性”、現代の暮らしではそれがリスクになる
猫が水をあまり飲まないのは、リビアヤマネコを祖先にもつ“本能”に由来します。もともと乾燥地帯で暮らしていたため、水をたくさん飲まなくても生きていけるように進化してきたのです。
しかし現代では、その本能が、かえって猫の健康を脅かすリスクになっています。
ドライフードが主食の家庭が多い現在、食事から十分な水分をとるのは難しく、飲み水の量が猫の健康を大きく左右する時代になっています。つまり、“飲まないのは仕方ない”ではなく、“飲まないままにしてはいけない”のです。
- 「水をあまり飲まない」は猫の習性と理解する
- 「でも水を飲ませる工夫は必要」と切り替える
- 水分補給は“管理する意識”が大切
猫は「水が足りない」と訴えてはくれません。だからこそ、飼い主さんが日頃の水分摂取を気にしてあげる必要があります。
まずは今日、いつもよりひとつ水皿を増やしてみるところから。その小さな一歩が、猫の未来を守る大きな変化につながります。
この記事はAIによって部分的に生成され、筆者である「いちろう」による編集と検証が行われています。




