
最近、給水器の水の減り方が遅い気がする…。
猫はあまり水を飲まない動物といわれますが、どのくらいの水分補給が必要なのでしょうか。
体重別の理想的な飲水量の目安は以下のようになります。
| 猫の体重 | 理想的な飲水量の目安 |
|---|---|
| 3kg | 90~150ml(/日) |
| 4kg | 120〜200ml(/日) |
| 5kg | 150〜250ml(/日) |
| 6kg | 180〜300ml(/日) |
この数値をヒトの体重に単純換算してみると、体重50kgで1.5〜2.5Lの水分が1日に必要なことになります。
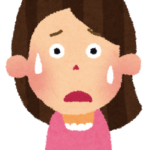
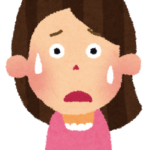
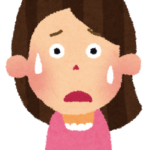
そう考えると必要な水分の量って多いんだね。
猫の飲水量は見落とされがちです。
特に日中仕事で留守にしている飼い主さんにとっては、飲水量を定期的に確認することは大変ですよね。
この記事では、「猫は水をどのくらい飲んでいるかどうか?」を自宅で確認するための5つの方法を紹介します。
目視でできる確認方法から、尿量のチェック、脱水サインの見分け方まで、今の状況に合わせて選べる実践的な方法をまとめました。





猫が飲んだ水の量って、いままで気にしてなかったな…。
飲水量のチェックは、猫の健康管理をする上で重要なバロメーターです。
この記事が猫の健康をチェックするきっかけになれば幸いです。


〈プロフィール〉
- 猫の飼育歴:6年目
- 迷い猫「くぅ」、保護猫「みり」と生活中
- 猫との遊びを充実させるアイテムを模索中
- キャトログを使い続けて【16ヶ月目】
猫は1日どのくらいの水を飲むの?
猫の祖先は、アフリカや中東の乾燥地帯に生息していた「リビアヤマネコ」。
砂漠のような過酷な環境で水を見つけるのは簡単ではなく、少ない水でも生きられるように猫の体は進化してきました。



どのくらいの水を飲んでいれば良いの?
猫は砂漠に住む動物で一般にはあまり水を飲まないとされており、理想的な1日の飲水量は体重1kgあたり30〜50ml程度です。
引用:猫が水を飲まない|猫のよくあるご相談|猫と暮らすお役立ち情報|ニャンとも清潔トイレ|エステー株式会社
体重ごとに計算すると、以下のような数値が理想的な飲水量のおおよその目安になります。(※これらの数値は普段ドライフードのみで過ごしている猫たちの目安です。)
| 猫の体重 | 理想的な飲水量の目安 |
|---|---|
| 3kg | 90~150ml (/日) |
| 4kg | 120〜200ml(/日) |
| 5kg | 150〜250ml(/日) |
| 6kg | 180〜300ml(/日) |
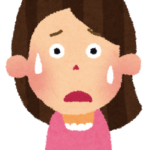
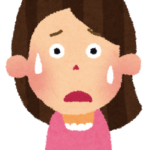
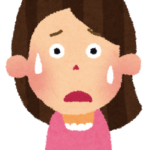
うちはウェットフードだから、こんなに飲んでないよ。
普段ウェットフードを食べている猫たちは、フードからも水分を摂取しています。
ウェットフードはカリカリよりもタンパク質と脂質の割合が多く、猫がおいしいと感じやすいようです。また、猫が野生下で食べる獲物に近い70〜85%という高い水分含量になっているため、より猫に好まれているのでしょう。
引用:岩崎永治.猫はなぜごはんに飽きるのか? 集英社 P.108
あげているウェットフードの水分含量をチェックしてみましょう。ウェットフードでカバーできている水分+飲水量が目安の量になります。
猫の水分補給、どうやって確認する?|3つのアプローチ方法



うちの猫、水をちゃんと飲めてるかな?
猫がきちんと水を飲んでいるかは、見た目だけだと判断が難しいですよね。
とくに一人暮らしの飼い主さんは日中の猫の行動を見守ることができないため、「ちゃんと飲めてるのかな…」という不安を抱えている方も多いかと思います。
猫の水分補給を確認する方法は、大きく分けて次の3つです:
- 水を飲んだか確認する方法(飲水量の確認)
- おしっこを確認する方法(尿量の確認)
- 体の変化を確認する方法(脱水の確認)
どの方法にもメリット・デメリットがありますが、状況に応じて組み合わせてみましょう。
猫の飲水量の2つの確認方法
まず「どのくらいの水を飲んでいるか?」をチェックしていきましょう。
ここでは、飲水量の変化をできるだけ簡単に確認できる方法を2つご紹介します。
メモリ付き水皿で水位の変化を見る
ざっくりとした飲水量を把握したい場合は、メモリ付きの水皿を使う方法がおすすめです。
毎回水を入れたときの高さを意識するのは難しいですが、水皿自体に目盛りがあれば、減った量がひと目でわかります。
特に一人暮らしの飼い主さんには、日々の変化を見逃さないための強い味方になります。
- 水面の変化が視覚的にわかる
- 印をつける必要がなく、衛生的
- 継続しやすく、習慣化しやすい
- 目盛りが細かくない場合、正確なmlまではわからない
- 器のデザインが限られる(好みが分かれる)
- 複数の水皿があると、管理がやや複雑になる
特別な道具も要らず、水皿を置き換えるだけで手間なく飲水チェックがスタートできます。
入れた水と戻した水の量を比べる
1日にどのくらい水を飲んでいるかを具体的に知りたいときは、「入れた水の量と戻した量を比べる方法」がわかりやすくて確実です。
やり方はとてもシンプルです。
朝水皿に入れる水の量をあらかじめ測っておき、夜に残った水を別容器に移して再び測るだけ。差分が、その日の飲水量のおおよその目安になります。
- 朝、水を計量カップなどで測って器に入れる
- 夜、残った水を別の容器に移し、再度測る
- 入れた量から残った量を引けば、その日の飲水量が推測できる
注意点としては、器の周りに水がこぼれていないかチェックすることです。とくに夏場は蒸発量が多くなりやすいので、数日間の平均を見る方が精度は上がります。
- ml単位で飲水量を具体的に把握できる
- 手軽にすぐ始められる
- 「水飲んでいないかも…」という不安を数字で判断できる
- 毎回測る手間がある
- 複数の水皿があると管理が大変
- 蒸発やこぼれた場合に誤差が出やすい
猫の尿量の2つの確認方法



飲水量はチェックできているけど、これだけで大丈夫かな?
飲水量をチェックするだけでは、猫の体調のすべてを把握することはできません。
しっかりと健康を見守りたいとき、注目したいのが“尿量のチェック”です。
猫は不調を隠す生き物。体の内側で起きている変化には、尿量や回数といった小さなサインが表れることがあります。
トイレの尿量を直接観察する
最も手軽で、すぐに始められるのがこの方法です。トイレの種類によって、尿量の確認方法は異なります。
- ペットシートを敷かずに、猫がおしっこをするのを待ちます
- おしっこをしたら、受け皿のおしっこを計量カップに移して、量を測定する
- 猫がおしっこするのを待ちます
- おしっこしたら、猫砂の大きさを観察します
- 50mlのおしっこだと、おおよそ7cm程の塊になります
システムトイレと比べると、ノーマルトイレは尿量を計測しにくい構造になっています。
尿量をチェックするのであれば、システムトイレの方がおすすめです。



尿量って、どのくらいが目安なの?
一例として体重5.0kgの猫のオシッコ一日量の目安は50〜150ccです。(参考:猫のオシッコ(尿)チェックの方法|猫の泌尿器ケア研究会|エステー株式会社)
次に尿の回数をチェックするようにしましょう。
- システムトイレ:ペットシートの尿の跡
- ノーマルトイレ:猫砂の塊の数



この方法だと、記録していくのが大変そうだね
これらの方法を継続的にチェックするのが難しいケースもあると思います。
まずは3ヶ月に1回などと頻度を決めて記録してみましょう。
Catlog Board2で尿量をml単位で記録する


より正確に、数字で体調管理をしたいなら、Catlog Board2(キャトログボード2![]()
![]()
おしっこの量をml単位で自動記録して、日々の変化をグラフで見られます。
- 昨日よりおしっこの量が少ない
- 最近、トイレに行く回数が増えている
- トイレに行ったけど、何もしていない



「トイレに行ったけど、何もしていない」って、大事な情報なの?
この情報めちゃくちゃ重要です!
「トイレに行ったけど、何もしていない」ということは、排尿にトラブルを抱えている可能性が疑われるからです。
単にトイレの量や回数を知るだけでなく、トイレに関わる時間を知るにはキャトログボード2![]()
![]()
- 「見た目」だけでは判断できない変化を数字で自動記録
- 多頭飼育でもそれぞれの猫のデータが把握できる
- 通院時にデータを見せて相談できる
- 留守中でも健康状態を見守れる
- 初期費用と月額費用が必要
- 測定数値に誤差がでることがある
- WI-FI環境が必要になる
\ クーポンコード「V7TAMZ」月額利用料2ヶ月分お得 /
クーポンが使えるのは公式サイトだけ!


飲んでないかも…と思ったら|脱水サインをチェック
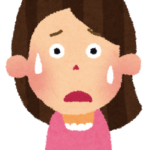
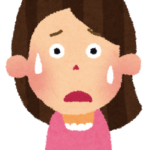
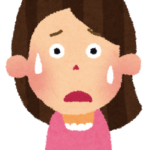
飲水量も尿量も確認してみてるけど、それでもなんだか心配…。
そんなときは、目の前の愛猫の体調をチェックできる”脱水サイン”に注目してみてください。
脱水の初期サインは、皮膚や歯ぐきといった見た目や触感にあらわれます。皮膚の張りをみるツゴール反応は、簡単にできるチェック方法なのでぜひ試してみてください。
皮膚の張りを見る(ツルゴール反応)
猫の肩甲骨あたりの皮膚を優しくつまんで持ち上げ、離してみてください。 通常ならすぐに皮膚が元の位置に戻りますが、戻るのが遅い場合は体内の水分が不足しているサインです。
- 判断目安:正常ならすぐ(1秒以内)に戻る
- 皮膚がゆっくり戻る・たるんだまま → 軽度〜中度の脱水を疑う
注意点:強くつままない・長時間行わないよう注意。老猫や痩せた猫は皮膚が戻りにくくなることがあるため、このチェックだけに頼らないようにしましょう。
実際に猫の脱水をチェックする様子を動画で見ておきたい方には、以下のYouTube動画がおすすめです。 「やり方が合っているか不安…」という方は、一度この動画で手順を確認しておくと安心です。
もしも不安なときは…
脱水のチェックはあくまで目安であり、診断ではありません。 脱水が疑われるときや、猫の元気が明らかにない場合は、すぐに動物病院で診てもらいましょう。
また、脱水は隠れた病気のサインであることも少なくありません。「様子を見よう」と迷う時間を減らすことが、命を守る第一歩になることもあります。
まとめ|猫に必要な水分を知って、しっかり健康管理


猫が普段水をどのくらい飲んでいるかどうかは、毎日接していても意外とわかりにくいものですよね。
そのため、飼い主さんが意識的に管理してあげることが重要になってきます。
| 猫の体重 | 理想的な飲水量の目安 |
|---|---|
| 3kg | 90~150ml(/日) |
| 4kg | 120〜200ml(/日) |
| 5kg | 150〜250ml(/日) |
| 6kg | 180〜300ml(/日) |
まずは、ご自身の猫さんたちに必要な飲水量を確認することが第一歩です。



目安と比べると、あんまり飲んでないかも…。
という不安があれば、まずはメモリ付きの食器から始めてみましょう。
データでしっかり見守りたい方には、キャトログボード2![]()
![]()
“なんとなく不安”をそのままにせず、今日からできる確認方法で猫たちの健康管理をより具体的に進めていきましょう。






