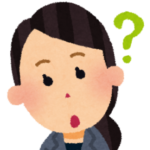
Catlog Board2が気になるけど…買って本当に役立つの?
本体が高価なうえに月額利用料もかかる。猫の健康管理に使えると分かっていても、「ただの記録で終わってしまわない?」と迷っている方は少なくないはずです。



「買っても使いこなせる?」と、僕も不安に思ってました。
今回、みりに起きた異変「トイレに行っても排尿していない」――最初に気づけたのはCatlogBoard2の記録の力でした。目では見逃してしまった小さな変化、それを教えてくれたのはアプリに蓄積された“数字”だったのです。
この記事では「CatlogBoard2を買って終わり」にしないために、データをどう使えば異変に気づけるのか?筆者が実際に体験した事例を元に、具体的な活用場面と導入して感じたリアルな価値をお伝えします。
記事を読み進める中で、CatlogBoard2 (キャトログボード2![]()
![]()
※この記事では「トイレ行動」を猫のおしっこ(排尿)に限定して扱っています。


〈プロフィール〉
- 猫の飼育歴:6年目
- 迷い猫「くぅ」、保護猫「みり」と生活中
- 猫との遊びを充実させるアイテムを模索中
- キャトログを使い続けて【16ヶ月目】
\ クーポン「V7TAMZ」月額利用料2ヶ月無料 /
クーポンが使えるのは公式サイトだけ!
Catlog Board2のデータが教えてくれた変化


毎日規則正しくトイレを使っている猫たちをみていると、「今日もちゃんとトイレしている!」と思い込んでしまいがちです。
今回筆者が経験したのは「トイレに入っているけど、実際には上手くおしっこできていない」というケースです。



毎日のトイレ掃除でも確認しているから、ちゃんと出てるかどうかは見てれば分かるよ。
たしかに、うんちであれば目視で確認しやすいですが、おしっこはそう簡単にはいきません。シートや砂の状態から判断するしかないため、微妙な変化には気づきにくいのです。
最初のサイン(1回あたりの尿量が減った)


2024年にCatlog Board2(キャトログボード2![]()
![]()



今日のおしっこはちょっと少ないかな?
「みり」の様子は普段と変わらず元気そうで食欲もあったため、最初は誤差なのかと深くは考えていませんでした。しかし、翌日のCatlogのデータにはおしっこ量の変化がはっきり現れるようになっていったのです。


トイレに入るだけで、おしっこがでない
遠目に見ている分には、「みり」はいつもと変わらずにトイレに入っているように見えました。



「トイレに滞在している時間」だけが増えてる?
しかし、CatlogBoard2(キャトログボード2![]()
![]()


猫の排泄行動は、以下のような理由で「見た目では判断が難しい」場合があります。
- トイレに入った回数だけでは実際に排泄したか分からない
- 排尿のポーズをとっても出ていないことがある
- おしっこをしていなくても、砂をかくことがある
「滞在だけして、実際にはトイレをしていない」というサインは、忙しい日常の中では見逃しやすいものです。日中留守にしていて不在になってしまう飼い主さんには特に発見が難しいかと思います。
「みり」の変化をCatlogBoard2のデータが気づかせてくれた


みりのおしっこ量が減ってから、明らかに「トイレに滞在しているだけ」の時間が増えてきました。
1回だけなら「そんなこともあるかな」と油断してしまいそうでしたが、Catlog Boardのデータは「みり」の変化をはっきり教えてくれたのです。
「なにもなければ良いし、一度動物病院に行ってみよう」と診察に向かうきっかけを与えてくれました。
\ クーポン「V7TAMZ」月額利用料2ヶ月無料 /
クーポンが使えるのは公式サイトだけ
動物病院での診断は「尿石症」


いつも通りご飯を食べて、いつも通り遊んでいる。Catlog Boardのデータに違和感を覚えた以外は、みりの体調に変わった変化はみられませんでした。
けれど、この時点で「動物病院へ行ってみよう」と判断できたのはCatlogの影響が大きかったと感じています。
病院に行く前に準備しておいたこと
- おしっこを採取しておいた
- Catlogアプリから排尿のデータをまとめておいた
近くの病院では精密検査が難しいことが分かっていたので、すぐに尿検査ができるように事前におしっこを採取しておきました。
ペットシートを一時的に外した状態にして、トレーをセットする。トレーにうけた「おしっこ」を紙コップなど別の容器に移し替えてラップする。こぼれないように気をつけてください。
今回はこの準備があったおかげで、尿石の検査までがスムーズに進みました。
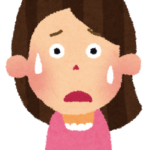
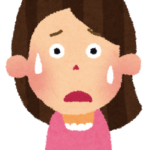
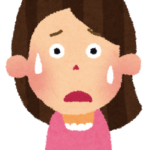
おしっこがうまく採取できるか不安…。
そんな場合は、おしっこチェックキットを準備しておくと便利です。スポイトが含まれるので、おしっこ採取も簡単でした。
もう一つ準備しておいてよかったことは、「みり」の状態を正確に伝えられるようにアプリのデータをまとめたことです。アプリ画面をスクリーンショットで保存して、最近の様子を説明できるようにしておきました。
- 一回のおしっこ量が減ったこと
- トイレに入っているけど、排泄していないことが増えたこと
- トイレに入る回数が増えたこと



今日はどうしましたか?



尿が出ていないっぽいんです。
漠然と猫の様子を伝えるよりも、「普段は1回で20mlくらいのおしっこしているですが、最近は8mlくらいしか出ないんです」と説明できると獣医さんもより状況を把握しやくなります。
このような細やかな情報もアプリ画面を使うことで、格段に伝えやすくなります。
「尿石症」の診断と療法食の開始後のおしっこ量の変化
事前におしっこを準備していたこともあり、尿検査からストルバイトが検出され「尿石症」と判明しました。



みりちゃんは「尿石症」ですね。



おしっこの量が減ってたのは、尿石の影響だったんですね。
療法食を嫌がってしまう猫も多いと聞いていましたが、「みり」はすんなりと受け入れてくれました。また、おしっこの量を増やす目的で水分摂取改善も進めていきました。
猫がどのくらい水を飲んでいるのかを確認するのは以外と難しく、今回はおしっこの量が増えているか確認する必要もありました。治療開始後のおしっこ量の変化も、Catlog Boardのデータが活躍します。


順調におしっこの量も増えていき、1ヶ月後の再検査では尿石はなくなっていました。治療後は「トイレに入ったけど、排泄しない」回数は明らかに減りました。
猫のトイレに関するトラブルを見逃さないーCatlog Board2の活用方法ー
ここまで筆者が実際に経験したエピソードをご紹介しました。Catlog Boardは確かに便利なアイテムであり、目で観察するよりも多くの情報を得ることができます。



僕の場合、CatlogBoardのデータが診察に行くきっかけになりました。
CatlogBoardを最大限活用するには、日々計測してくれる猫のトイレ情報を飼い主さんがチェックしつつ、実際に猫の様子も合わせて観察することが必要となってきます。
“記録を毎日見る”習慣をつける
Catlogアプリ画面を日頃から見るという習慣をつけることが重要です。CatlogBoardはトイレに関する情報をスマホに通知してくれますが、最後は飼い主さんが直接日々の変化をチェックすることが必要になってきます。
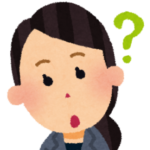
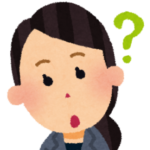
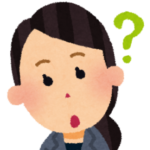
最近、1日のトイレ回数が少ない?



おしっこの頻度が多くなってる?
Catlog Boardのデータは普段の変化をチェックするのにとても便利ですが、おしっこの色やうんちの状態は直接観察しなければわかりません。猫の様子を直接チェックすることも忘れずに行いましょう。
確認すべきトイレに関わる3つのデータ


Catlogアプリは猫の様子に急な変化があった場合にアラートで教えてくれる機能があります。この機能はとても便利ですが、普段から猫の様子をチェックするために以下の3つの項目はチェックするようにしましょう。
- 1回あたりのおしっこ、うんちの量
- 1日あたりのおしっこ、うんちの回数
- トイレに入っているのに、排泄していない回数
今回は【1回あたりのおしっこ量】と【トイレに入っているのに排泄していない回数】が異変に気づくきっかけになりました。CatlogBoardを導入したら、これら3つの項目はしっかりチェックしていきましょう。
\ クーポン「V7TAMZ」で月額利用料2ヶ月無料 /
クーポンが使えるのは公式サイトだけ


「トイレに入っているのに排泄していない回数」の活用方法
例えば「トイレが汚れていて不満」や「トイレで落ち着いておしっこができない環境」があると、トイレに入っているのに排泄していない回数が増える要因になります。



最近、粗相されてしまうことがあって…。
猫トイレ以外で粗相してしまう理由は様々ですが、CatlogBoardを使うことで猫トイレ自体の異変に気づくきっかけにもなります。
まとめ:猫からのSOSサイン「トイレに入るけど、おしっこしない」
トイレに入っている様子を見ると「ちゃんと出ている」と思い込みがちですが、実際には排尿できていないこともあります。私もCatlogBoardを使う以前は、そんな小さな変化があってもまったく気づけませんでした。
Catlog Board2を使って排尿の量や回数が記録されるようになってから、「いつもと違うサイン」を見逃さずにすみました。今回は記録がきっかけで「みり」の尿石症を早期に発見し、スムーズに治療を始めることができました。
「うちの子も大丈夫かな?」と少しでも感じた方は、ぜひおしっこの様子を意識的に観察してみてください。記録があれば、飼い主の感覚だけに頼らず、冷静に判断しやすくなります。


すぐにCatlogを導入できない場合でも、おしっこの回数や量を簡単に記録するだけでも違います。大切なのは、“気づける仕組み”を日常に取り入れておくことです。
猫たちの健康を守るために、今できる一歩を踏み出してみてください。
\ クーポン「V7TAMZ」月額利用料2ヶ月無料 /
クーポンが使えるのは公式サイトだけ


